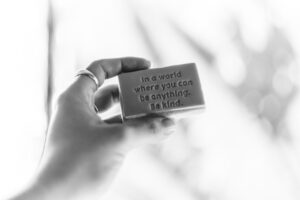あの日、私が実家の鍵を開けた瞬間に感じた「失敗」
玄関の鍵穴に鍵を差し込む。錆びついたような感触。回すのに力が要る。
「あ…」
扉を開けた瞬間、むせ返るようなカビと埃の臭いが顔を覆った。目の前には、父が大切にしていた玄関の絵が斜めに傾き、郵便受けからは数ヶ月分のチラシが床に散乱している。
2年前、私は「そのうち考えよう」と実家を放置する決断をした。
当時の私は、仕事と育児に追われ、遠方にある実家のことまで手が回らなかった。兄は海外赴任中。妹とは疎遠。「とりあえず誰も困っていないし、固定資産税だけ払っておけば…」そう思って先延ばしにしていた。
その「先延ばし」が、私から年間42万円を奪っていた
玄関を上がり、リビングに入る。畳は変色し、押し入れの襖は湿気で膨らんでいる。台所に行けば、水道管から水が滴り、床が腐食している。
固定資産税: 年12万円
火災保険: 年3万円
月1回の見回り交通費: 年18万円
突発的な修繕(今回の水漏れ): 9万円
計算すると、年間42万円。2年で84万円。この金額があれば、家族で海外旅行に2回行けた。娘の塾代も賄えた。
それよりも辛かったのは、心の奥底でずっと感じていた「罪悪感」だった。
「お父さんが大切にしていた家なのに…」
「いつか片付けなきゃいけないのに…」
「このまま朽ちていくのを見ているだけなんて…」
この記事は、かつての私のように「実家を放置している」あなたへ、私が学んだすべてを伝えるために書きました。
なぜ私は「とりあえず放置」を選んでしまったのか
実家が空き家になったとき、多くの人が同じ罠に落ちる。
❌ 一般的な対応:「とりあえず様子を見よう」
- まだ誰か住むかもしれない
- 思い出の品を整理する時間がない
- 売却や賃貸は手続きが面倒そう
- 「そのうち考えよう」で数ヶ月、数年…
私もまさにそうだった。父の死後、「心の整理がついてから」「もう少し落ち着いてから」と理由をつけては、現実から目を背けていた。
空き家放置がもたらす「見えない損失」の正体
放置期間が長くなるほど、失うものは増えていく。
| 損失の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 金銭的損失 | 固定資産税・維持費の継続支出 / 資産価値の目減り |
| 心理的損失 | 「いつかやらなければ」という罪悪感 / 家族間の気まずさ |
| 機会損失 | 売却・活用で得られたはずの収益 / 問題解決に使う時間と労力 |
| リスクの増大 | 老朽化による倒壊危険 / 近隣トラブル / 不法侵入 |
特に危険なのは「特定空き家」指定だ。
自治体から「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税額が最大6倍になる。私の実家も、あと1年放置していたら指定される可能性があった。
転機:隣の空き家が崩れた夜
それは、ある台風の夜のことだった。
スマホに実家の隣人から着信。「お宅の実家は大丈夫ですか?うちの隣の空き家の屋根が飛んできそうで…」
翌朝、ニュースで知った。隣町の空き家が倒壊し、通行人が怪我をした事故。所有者には損害賠償請求が…
「これは、明日の私かもしれない」
その瞬間、背筋が凍った。もし私の実家が誰かを傷つけたら?もし賠償金が数千万円になったら?
その日、私は決意した。「もう先延ばしにしない」と。
私が実家問題を解決するまでの90日間の記録
Phase 1: 現状把握と家族会議(1〜14日目)
最初にしたのは、実家の「本当の状態」を知ることだった。
地元の不動産業者3社に連絡し、現地調査を依頼。同時に、兄と妹にメールを送った。
メールの内容:
件名:実家について話したいことがあります
お疲れ様です。実家が危険な状態になっています。
放置すれば、私たち全員に法的・金銭的リスクがあります。
下記の資料を見て、来週末にオンラインで話しませんか?
- 現在の固定資産税と維持費
- 建物の劣化状況(写真付き)
- 近隣の同様物件の売却事例
感情的にならず、客観的な事実とデータで家族に現状を伝えた。
3日後、兄から返信。「正直、見て見ぬふりをしていた。話し合おう」
Phase 2: 選択肢の洗い出し(15〜30日目)
不動産業者との面談で、私には5つの選択肢があることを知った。
選択肢1: 売却
査定額:1,200万円(3社平均)
地元の不動産業者は、物件の立地や周辺環境、過去の修繕履歴などを考慮し、適正な査定額を算出してくれる。
メリット:
- まとまった現金が手に入る
- 固定資産税・維持費の負担ゼロ
- 精神的な解放感
デメリット:
- 売却までに平均3〜6ヶ月
- 仲介手数料(約40万円)
- 思い出の場所を手放す寂しさ
選択肢2: 賃貸
想定家賃:月7万円
メリット:
- 継続的な収入
- 将来的に売却も可能
デメリット:
- リフォーム費用(約200万円)
- 空室・滞納リスク
- 管理の手間
選択肢3: 解体・更地化
解体費用:約150万円
メリット:
- リスクの完全消滅
- 土地として売却しやすい
デメリット:
- 高額な初期費用
- 固定資産税が最大6倍に
選択肢4: 空き家バンク
自治体の制度活用
メリット:
- 仲介手数料が安価
- 移住者とのマッチング
デメリット:
- 成約まで時間がかかる
- 価格調整の必要性
選択肢5: 専門家への包括相談
弁護士・税理士・不動産会社の連携
複雑な相続問題や税務処理が必要な場合、ワンストップで解決できる。
Phase 3: 決断と実行(31〜90日目)
家族会議の結果、私たちは「売却」を選択した。
理由は明確だった。
- 兄も妹も将来的に住む予定がない
- 賃貸経営のノウハウがない
- 「早く心の重荷から解放されたい」という全員の本音
売却プロセスで学んだこと:
- 複数社への査定依頼が必須
1社目: 1,000万円 / 2社目: 1,200万円 / 3社目: 1,350万円
差額350万円。これを知らずに決めるところだった。 - 簡易清掃で印象が激変
業者に頼んで不用品を処分し、水回りを清掃。内覧時の印象が全く変わった。 - 売却時期の見極め
春(1〜3月)の繁忙期を狙って売り出し。2ヶ月で買主が見つかった。
最終的な売却価格:1,280万円
仲介手数料や諸費用を引いて、手元に残ったのは約1,200万円。
あの日から1年:私が手に入れたもの
売却から1年。私の生活は大きく変わった。
金銭的な変化
- 固定資産税の負担ゼロ: 年12万円の支出がなくなった
- 売却益の活用: 娘の教育資金として500万円を積立、残りは老後資金へ
- 見回り交通費ゼロ: 年18万円と移動時間の節約
精神的な変化
何よりも大きかったのは、心の平和だった。
「いつかやらなければ」という漠然とした不安が消え、毎晩ぐっすり眠れるようになった。家族との関係も、実家問題を通じて深まった気がする。
学んだ教訓
❌「そのうち考えよう」は、最もコストの高い選択
✅「今すぐ動く」が、最も賢い選択
あなたが今日からできる3つのアクション
アクション1: 現状把握(今日〜1週間)
実家の状態を正確に知る。
- □ 実家の写真を撮る(外観・内部・劣化箇所)
- □ 直近3年分の固定資産税納付書を確認
- □ 年間維持費を計算(保険・交通費・修繕費)
アクション2: 家族会議(1〜2週間)
関係者全員で情報共有。
- □ 現状データをまとめた資料を作成
- □ オンラインでも対面でも、全員が参加できる場を設定
- □ 感情ではなく事実に基づいて話し合う
アクション3: 専門家相談(2〜4週間)
必ず複数の専門家に相談すること。
- □ 地域の不動産業者3社以上に査定依頼
- □ 自治体の空き家対策窓口に相談
- □ 必要に応じて税理士・弁護士に相談
【重要】この記事の情報だけで判断しないでください
この記事は、私の実体験と調査に基づいて書かれていますが、不動産の売買、相続、税務は非常に専門的かつ個別性の高い領域です。
以下の点に必ずご注意ください:
⚠️ 法的・税務的なアドバイスではありません
個々の状況により適用される法律や税制は異なります。必ず弁護士・税理士にご相談ください。
⚠️ 価格や費用は地域・時期により変動します
本文中の金額はあくまで参考例です。実際の査定は専門業者に依頼してください。
⚠️ 家族関係や感情面の配慮も重要です
経済合理性だけでなく、家族の思いや将来の関係性も考慮した判断が必要です。
推奨する相談先:
- 不動産会社(売却・賃貸)
- 税理士(税務処理)
- 弁護士(相続・法的問題)
- 自治体の空き家対策窓口
まとめ:あなたの「明日」は今日の決断で変わる
冒頭で話した、カビ臭い玄関で立ち尽くしていた私。
あの日から90日間、私は動いた。そして人生が変わった。
あなたにも、同じ未来が待っている。
「実家 誰も住まない どうする」という悩みは、決して一人で抱え込む必要はない。選択肢は必ずある。そして、今日動き出せば、90日後には新しい未来が始まっている。
この記事が、あなたの最初の一歩を後押しするきっかけになれば幸いです。